TAX CONTENT
税金情報&お知らせ
輸入仕入(貿易)の仕訳は、いつの日にするのか?
海外から商品や材料を仕入れる場合には、いくつかの仕入の計上基準があります。中小企業では、単純で分かりやすい日が良いと思いますので、そちらを確認しておきましょう!

1.仕入計上基準を知っておく
輸入して仕入れる場合には、いくつかの基準があります。せっかくですので、まずは名前だけでも確認しておきましょう。
<輸入仕入れの計上基準>
・船積通知入手日基準
・船荷証券入手日基準
・通関日基準
・商品引取日基準
・検証基準
など、たくさんあります(*^^*)
ただ日本の税法では、「これにしなさい!」というルールがある訳ではないので、各々の会社でルールを作る必要があります。
また貿易であれば、インコタームズで様々な貿易条件が決められていますが、それも日本の税務とは一切関係ありません。分かりにくいですよね(笑)
2.「商品引取日基準」で全てOK
では、中小企業の経理においては、何を使ったらよいのでしょうか?
経理を複雑にするのはナンセンスです。
そのため単純明快である、『商品を受け取った時点で仕入』が一番分かりやすいでしょう(^-^)v
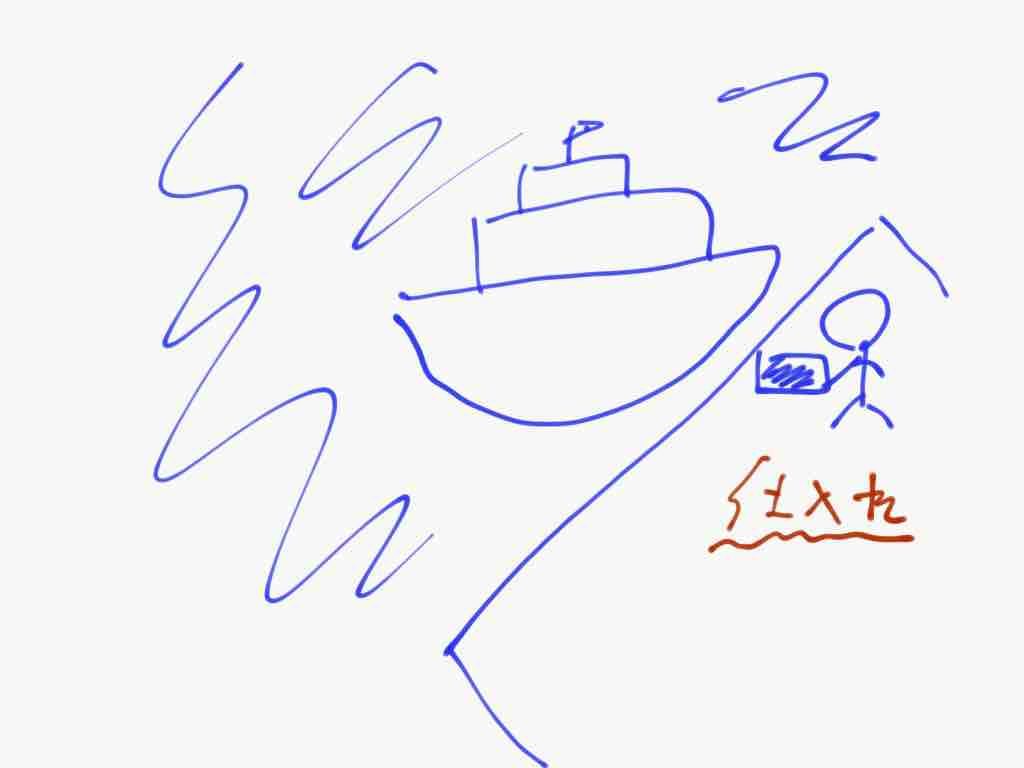
お堅い本には「未着品」勘定を使って、あーだ、こーだ書いてありますが、未着なら別に処理する必要ないでしょ(笑)
よって、実際に保税地域から商品を受け取った時点、または会社に到着した時点で仕入れを計上してください。
ある程度の取引規模になって、輸入の書類で全て管理し、仕入債務なども把握しておきたいのであれば、船荷証券入手日や、通関日基準で良いでしょう。
3.税務調査で確認されるところ
この仕入れ計上日が曖昧であれば、税務調査では突っ込みどころ満載になります(*^^*)
例えば、「通関日基準」で仕入れを計上していたとしましょう。
それが会社の決算日時点で商品が到着していなければ、在庫(未着品や棚卸し)として計上しなければいけませんが、忘れることが多々あります。
そうすると、仕入れの経費となっており『在庫の計上漏れ』ということで、「在庫の金額×法人税率」で税金を払うはめになります。
しかし、商品を引き取った時点で仕入れを計上するルールにしておけば、期末時点では商品は引き取っていないので、そもそも帳簿には何も計上していません。
そしたら決算で間違いもなく、税務調査でも指摘されないのです(^ ^)
2年間で考えれば払う税金は変わりはありませんが、税務調査で指摘されれば、「延滞税や過少申告加算税」を払う必要があります。こんなのもったいないですよね。
また人間同じ額を払うにしても、先に正しく払っておけばなんとも思わないのですが、数年後、税務調査で同じ額を払わされると嫌な気分になるものです(笑)
不思議ですよねー。
4.まとめ
ということで、海外から商品や材料を輸入するときには、『商品を受け取った時点で仕入』という、分かりやすいルールが良いかと思います。
物が無いのに仕入れとなるのは違和感がありますからね。できるだけ「八百屋のカゴ会計」が良いのです(^ ^)
<注意>
こちらの記事は、中小企業の経営者や経理担当者に分かりやすく書いています。そのため細かな詳細は省いておりますので、ご不明なことは顧問税理士さんか税務署、または当事務所までご相談ください(*^^*)





